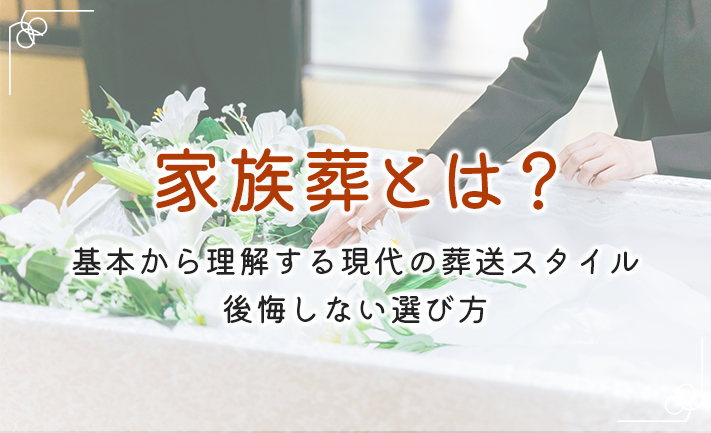
2025.05.16(金)
- 葬儀
家族葬とは?基本から理解する現代の葬送スタイル|後悔しない選び方
突然の別れに戸惑いながらも、大切な人のために最適な「送り方」を考えたいという思いは誰にでもあるものです。
家族葬という選択肢が広く知られるようになりましたが、実際にどのようなものなのか、どんな準備が必要なのか、わからないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、家族葬について基本から詳しく解説していきます。
はじめに
葬儀のあり方は時代とともに変化してきました。かつては地域ぐるみの大規模な葬儀が一般的でしたが、現在では故人や家族の意向を重視した「家族葬」が選ばれることが増えています。
この記事では、葬儀についての知識が少ない方でも理解できるよう、家族葬の基本から実践的なアドバイスまで詳しく解説していきます。急な対応が必要になった方も、事前に知識を得ておきたい方も、この記事を参考に、後悔のない選択をしていただければ幸いです。
家族葬とは?
「家族葬」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのようなものなのか、一般的な葬儀とどう違うのかわからない方も多いでしょう。家族葬は単に「小規模な葬儀」というだけでなく、故人と遺族の関係性を大切にした、現代的な葬送のあり方を表しています。まずは家族葬の基本的な特徴から見ていきましょう。
家族葬という言葉に明確な定義はありませんが、一般的には「近親者や親しい友人など、限られた人たちで行う小規模な葬儀」を指します。参列者は10〜30人程度が多く、親族を中心に故人と親しかった方々で行われるのが特徴です。家族葬は規模を小さくすることで、より故人との思い出に集中でき、静かに別れを告げることができる点が大きな魅力となっています。
■家族葬の定義と一般葬との違い
家族葬と一般葬(または社葬・団体葬など)の主な違いは以下の点にあります。
- 参列者の規模:家族葬は近親者を中心とした小規模な参列者で行われます。一般葬では50人〜数百人規模になることもあります。
- 葬儀の流れ:家族葬では通夜を省略したり、告別式を短縮したりするなど、簡略化されることが多いです。
- 費用面:参列者が少ないため、会場費や飲食費、返礼品などの費用が抑えられる傾向にあります。
- 準備期間:一般葬に比べて準備の負担が少なく、短期間での実施も可能です。
- 雰囲気:より親密で、故人との個人的な思い出に焦点を当てた、静かで落ち着いた雰囲気で執り行われることが多いです。
家族葬は「小さな葬儀」ではなく、「故人と遺族の関係性を中心に据えた葬送のあり方」と捉えることが大切です。形式や規模よりも、故人を偲ぶ「質」を重視した選択肢といえるでしょう。
家族葬が選ばれる理由と背景
近年、家族葬を選ぶ人が増えている背景には、社会的・経済的な変化があります。
- 核家族化の進行
- 地域コミュニティとの繋がりが希薄になり、大規模な葬儀の必要性が低下
- 親族間の関係も変化し、遠方の親戚が集まることが難しくなった
- 価値観の多様化
- 形式にとらわれず、故人らしさを大切にする傾向の高まり
- 個人の意思や家族の思いを重視する文化の浸透
- 経済的な理由
- 葬儀費用の負担軽減を望む声の増加
- 合理的な支出を考慮した選択肢として注目
- 高齢化社会の影響
- 高齢の参列者への配慮として、負担の少ない形式を選ぶケース
- 身近な人を続けて亡くす状況で、その都度の大規模葬儀が現実的でない場合も
家族葬は「簡素にすませる」というネガティブな選択ではなく、現代の家族のあり方や故人との関係性に合わせた、積極的な選択肢になっています。社会のニーズの変化に応じて、葬儀のかたちも多様化しているのです。
家族葬の基本的な流れと特徴
一般的な家族葬の流れは以下のようになります。ただし、地域や宗教、家族の希望によって異なる場合がありますので、参考程度にご覧ください。
- お亡くなりになってから24時間以内
- 医師による死亡確認
- 葬儀社への連絡
- 近親者への連絡
- 葬儀の形式(家族葬)の決定
- 2〜3日目
- ご遺体の安置
- 葬儀の打ち合わせ(日程、場所、参列者範囲など)
- 故人の身支度(お化粧、着替えなど)
- 通夜(省略する場合も)
- 3〜4日目
- 告別式
- 火葬
- 収骨
- 初七日法要(近年は「一日葬」として当日に行うことも)
- その後
- 四十九日法要
- (必要に応じて)参列できなかった方への挨拶や報告
家族葬の特徴は、それぞれの行程をより簡潔に、家族の意向に沿って柔軟に行える点にあります。例えば、通夜を行わず一日で全ての儀式を終える「一日葬」や、火葬のみを行う「直葬」なども家族葬の一形態として選ばれることがあります。
また、参列者が少ないからこそ、一人ひとりが故人にじっくりと向き合える時間を持てることも大きな特徴です。返礼品の用意や、思い出の品の展示、好きだった音楽を流すなど、故人らしさを表現する工夫も取り入れやすくなっています。
長野県における葬儀習慣の特徴
葬儀の流れや作法は、地域によって少しずつ違いがあります。長野県もそのひとつ。ここでは、長野でよく見られる葬儀の特徴を、簡単にご紹介します。
- 火葬を先に行うのが一般的
長野では、通夜の翌日に火葬をしてから、葬儀を行う「前火葬」のかたちが多く見られます。火葬のあと、お骨を前にして葬儀を行うので、「骨葬」とも呼ばれています。全国的には葬儀のあとに火葬を行う流れが主流(70%強)ですが、長野ではこの順番が自然と受け入れられています。 - 通夜はごく身内だけで静かに
通夜は親族など、ごく近しい方だけで行うのが一般的。一般弔問受付(告別式)は、葬儀当日の少し前(だいたい1時間前くらい)に受け付けることが多いです。バタバタしがちな通夜を、落ち着いた時間にしておきたい、という気持ちが表れているのかもしれません。 - ご近所とのつながりを大切にする風土
長野県では、人生の節目を大切にする風習があり、葬儀にはご近所の方や地域の方が参列されることも多いのが特徴です。そのため、葬儀後の酒食によるおもてなしの席も比較的多人数になることがあります。ただ、近年はコロナの影響もあり、少しずつ簡素なかたちへと変わりつつあります。 - 「お香典」と一緒に「お見舞い」を渡す習慣も
香典袋は黒白の水引が一般的ですが、地域によっては赤白の水引を使った「お見舞い金」を一緒に渡す習慣があります。これは、病気で亡くなった方に対して「最後のお見舞い」を届けるような気持ちからきているそうです。
土地によって、葬儀のかたちはさまざま。でも大切なのは、故人とのお別れの時間を、家族や親しい人たちでしっかり持つこと。長野の風習に沿いつつ、ご家族らしい送り方ができれば、それが一番なのかもしれません。
【緊急時ガイド】急な対応が必要になったときの家族葬の進め方
突然の訃報に接し、何から手をつければよいのか分からない状況は誰にでも起こりえます。緊急時には冷静さを保ちながら、必要な手続きを順に進めていくことが大切です。ここでは、お亡くなりになってから葬儀までの流れを、時系列に沿って解説します。
感情的に動揺している中でも、この順序を頭に入れておくことで、必要な対応がスムーズに進められるでしょう。まずは深呼吸をして、一つずつ確実に進めていくことを心がけてください。
■亡くなった直後にすべき連絡と手続き
お亡くなりになった直後には、以下の連絡と手続きが必要です。状況や場所によって順序が前後する場合もありますが、基本的な流れとして押さえておきましょう。
- 医師への連絡(死亡診断書の発行)
- 病院でお亡くなりの場合:病院のスタッフが対応してくれます
- 自宅でお亡くなりの場合:かかりつけ医または救急(119番)に連絡
※医師による死亡確認と死亡診断書の発行が必須です
- 葬儀社への連絡
- 24時間対応の葬儀社が多いので、死亡診断書が発行されたらすぐに連絡
- この段階では「家族葬を検討している」と伝えておくとよいでしょう
- ご遺体の搬送や安置について相談
- 近親者への連絡
- まずは直近の家族(子供、兄弟姉妹等)
- 次に親戚(甥・姪、いとこ等)
- 電話が難しい場合は、LINEやメールで「至急連絡してほしい」と伝えるのも一つの方法
- 職場への連絡
- 故人が現役で働いていた場合は、職場への連絡も必要
- 亡くなった事実と、葬儀の予定について(決まっていれば)
この段階では詳細が決まっていなくても問題ありません。「家族葬を予定している」「詳細が決まったら連絡する」といった伝え方で十分です。大切なのは、必要な人に必要な情報をタイムリーに伝えることです。
また、連絡する際には自分自身の心身の状態にも気を付けましょう。感情的になりすぎる場合は、家族や親族に連絡役を代わってもらうことも検討してください。
■24時間以内に決めるべき重要事項
死亡確認から24時間以内に、以下の重要事項を決める必要があります。家族で相談しながら、故人の意向も考慮して決めていきましょう。
- 喪主の決定
- 一般的には配偶者や長子が務めることが多い
- 高齢などの理由で負担が大きい場合は、実務面をサポートする「喪主代行」を立てることも
- 喪主は葬儀社との契約や香典の管理など、重要な役割を担います
- 葬儀の形式の決定
- 家族葬とすることの最終確認
- 通夜を行うか、一日葬とするか
- 宗教や宗派の確認(故人の信仰に合わせた対応が必要)
- 葬儀の日程と場所
- 主要な参列者(近親者)のスケジュール確認
- 葬儀会場の予約(葬儀社の斎場、公営斎場、寺院など)
- 僧侶・神職などの手配(宗教がある場合)
- 参列者の範囲の決定
- 「家族のみ」なのか「親族まで」なのか「親しい友人まで」なのかの線引き
- 参列者への連絡方法(直接電話、メール、SNSなど)
- ご遺体の安置場所
- 自宅、葬儀社の安置施設、病院の霊安室など
- 面会できる時間や条件の確認
これらの決定事項は、後の準備をスムーズに進めるために重要です。特に葬儀の日程と場所は、参列者の予定調整や葬儀社の手配に直結するため、優先的に決めるとよいでしょう。
決断に迷う場合は、「故人ならどう望むだろうか」「家族が最も心安らかに送り出せる方法は何か」という観点から考えてみることをおすすめします。
■葬儀社の選び方と依頼する際のポイント
家族葬を執り行うためには、信頼できる葬儀社選びが重要です。急な状況でも、以下のポイントを参考に選びましょう。
<事前の情報収集>
- 時間的余裕がない場合は、知人の紹介や評判を参考に
- 可能であれば複数の葬儀社に見積もりを依頼
- 特に家族葬に対応実績がある葬儀社かどうかを確認
<見積もりのチェックポイント>
- 基本プランに含まれるものと別料金になるものの明確な区分
- 追加料金が発生する可能性がある項目のチェック
- 支払い条件(前払い、後払い、分割など)の確認
<コミュニケーション重視>
- 丁寧な説明をしてくれるか
- 家族の意向を尊重してくれるか
- 押し売りのような提案はないか
葬儀社との打ち合わせには、可能であれば家族複数人で参加し、それぞれの視点から質問や確認を行うことをおすすめします。一人では聞き逃してしまうポイントも、複数人で確認することでより安心できる葬儀の準備が進められます。
家族葬の費用相場と内訳を徹底解説
葬儀の費用は多くの方にとって大きな関心事です。
家族葬は一般的な葬儀よりも費用を抑えられることが多いですが、何にいくらかかるのか、内訳を理解しておくことが大切です。
全国の家族葬の平均費用は約100万円〜150万円ですが、地域や内容によって大きく変動します。
■家族葬の平均費用と費用を左右する要素
全国の家族葬の平均費用は、約100万円〜150万円と言われています。ただし、これはあくまで平均値であり、以下の要素によって大きく変動します。
- 地域差
- 都市部(特に東京、大阪など):130万円〜200万円
- 地方都市:80万円〜150万円
- 田舎・郊外:70万円〜120万円
- 参列者数
- 10人以下の少人数:80万円〜100万円
- 20人前後:100万円〜150万円
- 30人以上:150万円〜200万円
- 葬儀の内容
- 一日葬(通夜なし):一般的に10〜20%安くなる傾向
- 直葬(告別式なし、火葬のみ):30万円〜50万円程度
- 宗教者の有無:僧侶への謝礼(お布施)が必要かどうか
- 葬儀会場
- 葬儀社の専用ホール:基本料金に含まれる場合と別料金の場合あり
- 公営斎場:比較的安価(5万円〜15万円程度)
- 自宅:会場費は不要だが、設営費が必要
家族葬の費用を左右する最大の要素は、参列者数と選択するオプションの量です。同じ「家族葬」でも、内容によって50万円から200万円以上まで大きな幅があることを理解しておきましょう。
また、近年では「家族葬プラン」として葬儀社が定額パッケージを提供していることも多いですが、基本プランに含まれるものとオプション扱いになるものの境界があいまいなケースもあります。見積もりの際は具体的に確認することをおすすめします。
平安祭典では、さまざまなご要望に対応した家族葬プランをご用意しております。予算やご希望に合わせてお選びいただける家族葬プランの詳細は、下記の「家族葬プラン」ボタンからご確認いただけます。事前のご相談も24時間承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
家族葬でよくある疑問と不安
家族葬を検討する際、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問について簡潔に回答します。
■参列者を決める基準
参列者を決める際は、以下のポイントを参考にしてください:
- 血縁関係の近さ(一親等、二親等など)
- 故人との親密度(頻繁に交流があったか)
- 故人の生前の希望(「あの人には来てほしい」など)
大切なのは、意思決定の理由を明確にし、丁寧に伝えることです。例えば「故人の遺志により、近親者のみでお見送りすることになりました」「高齢の遺族の負担を考慮し、小規模な家族葬とさせていただきます」など、理由を添えることで理解を得やすくなります。
■通夜は必要?
家族葬では通夜を省略し、告別式のみを行う「一日葬」が増えています。通夜を行うと故人と過ごす時間をより長く持てる一方で、通夜を省略すれば遺族の肉体的・精神的負担軽減や費用面での節約になります。
宗教者に依頼する場合は、「一日葬でも問題ないか」を事前に確認しておくことをおすすめします。宗派によっては通夜を省略することに抵抗がある場合もあります。
■香典の扱い
家族葬における香典の扱いについては、以下の選択肢があります:
- 香典辞退の場合: 案内状に「ご厚志は固くご辞退申し上げます」と明記、または受付に「香典辞退」の札を立てる
- 香典を受け取る場合: 通常通り受付で預かり、後日の返礼品を準備する
地域性や文化的背景による違いも大きいため、地域の慣習も考慮して決めるとよいでしょう。
より詳しい対処法や具体的な例については、「家族葬でよくある疑問と対処法」の記事で詳しく解説する予定です。
その他、葬儀後に「こうしておけば良かった」という後悔をしないために、事前に確認しておくべき重要なポイントがあります。故人の意向確認から参列者の範囲、宗教的な配慮まで、家族葬で後悔しないためのチェックポイントの詳細については「家族葬で後悔しないための5つのチェックポイント」をご覧ください。
【まとめ】本当に大切なのは「形」ではなく「想い」
葬儀は文化的・社会的な儀式である一方、極めて個人的な「お別れの場」でもあります。家族葬を選ぶ際の本質的な考え方として、以下の点を大切にしてください:
- 故人の意向を最優先に
- 明確な意思表示があれば、それを尊重する
- 生前の言動や価値観から推測できる部分を大切に
- 遺族の心の整理ができる形を選ぶ
- グリーフケア(悲嘆からの回復)の観点からも適切な選択を
- 遺族自身が納得できる選択であること
- 本質的な目的を見失わない
- 葬儀の本来の目的は「故人を送ること」と「遺族の心の整理」
- 形式や慣習に縛られすぎないこと
決断に迷ったときは、「この選択は5年後、10年後に振り返ったときに納得できるものか」と自問してみることも有効です。形式的な選択よりも、心からの「送り方」を重視することで、長い目で見たときの後悔も少なくなるでしょう。
家族葬という選択肢は、現代の多様化とパーソナライズの流れの中で生まれてきたものです。葬送の形は変化し続けますが、「故人を敬い、遺族が心の整理をつける場」という本質は変わりません。
形式ではなく、その中身に込められた想いこそが、本当の意味で故人を送る葬儀の核心なのです。どのような形であれ、故人への感謝と敬意を表し、思い出を共有する場として、有意義な「お別れ」の時間となることを願っています。
 家族葬の定義についてはこちら
家族葬の定義についてはこちら 平安祭典の家族葬について詳しく見る
平安祭典の家族葬について詳しく見る


