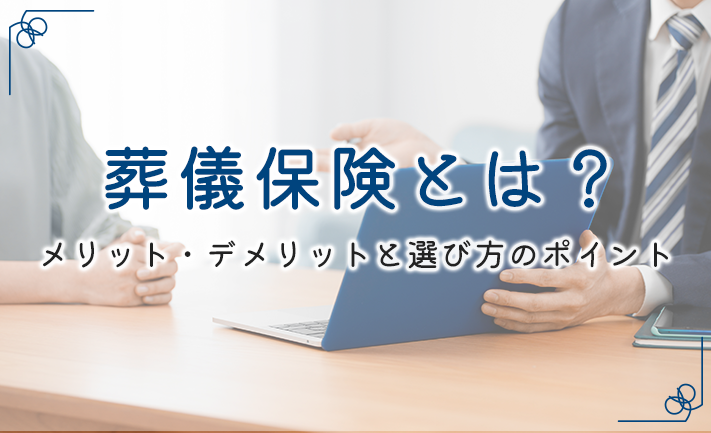
2025.08.21(木)
- 終活
- 葬儀
葬儀保険とは?メリット・デメリットと選び方のポイント
はじめに
「もしもの時」に必要となるのが葬儀費用です。突然の葬儀では数十万〜数百万円が必要になり、遺族にとって大きな負担となることも少なくありません。その備えとして注目されているのが「葬儀保険」です。
本記事では、葬儀社として実際に数多くのご葬儀をお手伝いしてきた立場から、葬儀保険の仕組みや種類、メリット・デメリット、さらに失敗しない選び方のポイントまでを徹底解説します。
1. 葬儀保険とは?仕組みと種類を徹底解説
■葬儀保険の基本的な仕組み
葬儀保険は、葬儀にかかる費用を準備するための少額短期保険です。一般の生命保険と異なり、死亡保険金が数千万円単位ではなく、100万〜300万円程度と必要最小限に設定されています。
特徴は、加入手続きが簡単で、支払われる保険金も迅速であること。遺族が急な費用に困らないよう設計されています。
■葬儀保険の主な種類
- 掛け捨て型:保険料を支払い続ける限り保障が続き、被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われます。
- 月々の保険料は安いが、亡くならなければ保険金は支払われず、解約返戻金もほとんどない。
- シンプルに「葬儀代を備えたい」方向け。
- 積立型:保険料の一部が積み立てられ、満期時や途中解約時に解約返戻金として戻ってくる仕組みです。
- 保険料がやや高めだが解約返戻金があり、保障と貯蓄の両方の機能を持っている。
- 「万一の備え」と「資産形成」の両方を考えたい人に向く。
■葬儀保険で何がカバーできる?
葬儀保険でカバーできる範囲は、基本的に葬儀全般の費用です。具体的には以下のようなものが含まれます。
- 葬儀社への基本料金(祭壇、棺、ご遺体の搬送・安置費用など)
- 火葬場使用料
- 会葬返礼品や供花の費用
- 僧侶へのお布施や戒名料
- 通夜・告別式の会場費や飲食費
ただし、保険金額には限度があり、一般的に100万円から300万円程度のものが多いです。そのため、特に大規模な葬儀を希望する場合や、地域によっては費用が保険金額を超えることもあります。葬儀会社の立場からすると、葬儀の規模や内容によって費用は大きく変動するため、保険金額の設定は慎重に行うことをお勧めしています。
2. 葬儀にかかる費用の実態|保険に入る前に知るべきこと
葬儀保険を検討する前に、実際の葬儀費用について理解しておくことが重要です。葬儀費用は地域や葬儀の規模、スタイルによって大きく異なります。葬儀会社として多くの葬儀を執り行ってきた経験から、保険選びの参考になる費用の実態をお伝えします。
■全国平均と相場
鎌倉新書「第6回・お葬式に関する全国調査(2024年)」によれば、葬儀費用の全国平均は118.5万円。2013年の約203万円から10年で大きく下がり、直近ではコロナ禍の影響を経てやや回復傾向にあります。
■葬儀形式による費用差
近年、葬儀のスタイルは多様化しており、選ぶ形式によって費用は大きく変わります。
- 一般葬:約161万円
- 家族葬:約106万円
- 直葬・火葬式:約43万円
このように葬儀の形式によって費用差は大きいため、将来どのような葬儀を希望するかによって、必要な保険金額も変わってきます。現在の傾向として家族葬が増加していることも、保険金額を検討する際に考慮すべき点です。
■見落としがちな追加費用
葬儀保険に加入する際、多くの方が見落としがちなのが葬儀社以外に発生する追加費用です。葬儀社への支払い以外にも、様々な費用が必要になります。
- お布施・戒名料: 宗派や地域によって金額は異なりますが、10~50万円程度が相場です。
- 火葬料金: 自治体や火葬場の種類によって異なりますが、公営の場合は数万円、民営の場合は10万円前後かかることが多いです。
- お墓や納骨にかかる費用: 既存のお墓がない場合、新たに墓地や納骨堂を購入する費用が別途必要です。
- 会食費: 参列者への振る舞いとして会食を行う場合、一人あたり5,000~10,000円程度の費用がかかります。
- 相続や各種手続きの費用:相続登記や税申告などで専門家に依頼する場合は、数万円〜数十万円の費用が発生することがあります。
これらの追加費用を考慮せずに保険金額を設定すると、実際に葬儀を行う際に予算が不足する可能性があります。葬儀会社としての経験から、葬儀保険に加入する際は、葬儀社への支払い以外の費用も含めた総額で検討することをお勧めしています。
3. 葬儀保険の5つのメリット・デメリット
葬儀会社として数多くのご遺族と接してきた経験から、実際の現場で感じる葬儀保険のメリット・デメリットについてお伝えします。
【メリット①】葬儀費用の備えになる
葬儀や法要に必要な数十万円〜数百万円を、遺族に負担させずに済みます。突然の出費に対する経済的な備えとして非常に有効です。故人との大切なお別れの時間に、費用の心配をせずに集中できるようになります。
【メリット②】加入が比較的容易
医療保険よりも告知内容が簡単な場合が多く、高齢者や持病のある方でも入りやすい商品が多いです。特に簡易告知型や無告知型の商品では、健康状態にかかわらず加入できるものもあります。
【メリット③】少額から加入できる
毎月の保険料は数千円〜と比較的負担が小さく、長期間かけて計画的に準備できます。特に若いうちから加入すれば、月々の負担は非常に少額で済みます。
【メリット④】遺族への手続きがスムーズ
死亡時に迅速に保険金が支払われる仕組みが整っているため、葬儀費用の支払いなど急な出費に対応しやすいです。一般的な生命保険と比べて、死亡保険金の請求手続きが簡素化されている商品も多いです。
【メリット⑤】目的が明確で安心感がある
「葬儀代はこれでまかなえる」という明確な目的があることで精神的な安心を得られます。自分自身が入ることで「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちを形にできる点も大きなメリットです。
=====
【デメリット①】掛け捨て型が多い
保障期間内に亡くならなければ受け取れるお金がなく、払った保険料が無駄になる可能性があります。特に若い方にとっては、費用対効果の面で疑問を感じることもあるでしょう。
【デメリット②】長生きすると割高になる
高齢まで支払いを続けると、結果的に葬儀費用を上回る保険料を払うこともある点は注意が必要です。長寿化が進む現代では、このリスクは無視できません。
【デメリット③】保障額は限定的
一般的に保険金額は100〜300万円程度で、盛大な葬儀を希望すると不足する可能性があります。特に都市部での葬儀や参列者が多い場合には、保険金だけでは足りないケースもあります。
【デメリット④】途中解約は損になりやすい
解約返戻金が少ない、または全くないことが多いため、途中で解約すると支払った分が戻らないことがあります。加入前には将来の経済状況も考慮した保険料設定が重要です。
【デメリット⑤】インフレや葬儀費用の変化に対応しづらい
契約時に保険金額が固定されるため、葬儀費用が将来上がった場合、保険金額が不足するリスクがあります。また葬儀のスタイル自体も時代とともに変化しており、将来のニーズとのミスマッチが生じる可能性もあります。
これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、自分自身や家族の状況に合った選択をすることが重要です。葬儀保険は有効な備えの一つですが、他の準備方法と組み合わせて総合的に考えることをお勧めします。
4. 葬儀保険の選び方|失敗しないための重要ポイント
葬儀保険を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。葬儀会社として多くのご遺族と接してきた経験から、後悔しない選び方のポイントをご紹介します。
■ポイント①: 保険金額の適切な設定方法
保険金額は希望する葬儀の形式や地域の相場を考慮して設定しましょう。一般葬なら150~250万円程度、家族葬なら80~150万円程度が目安です。将来の葬儀スタイルの変化も考慮し、柔軟性を持たせた金額設定が理想的です。
■ポイント②: 支払い条件と受取人の正しい選択
保険金の支払条件(いつ、どのような場合に支払われるか)を必ず確認しましょう。また受取人は葬儀の喪主になる可能性が高い方を指定するのが望ましいです。複数の受取人を指定できる商品もあるので、家族構成に合わせて検討してください。
■ポイント③: 葬儀社との連携が取れているかの確認方法
葬儀保険の中には特定の葬儀社と提携しているものもあります。葬儀社との連携がスムーズな保険を選ぶと、葬儀の手配から保険金の活用まで一貫してサポートを受けられる場合があります。事前に提携葬儀社の範囲や対応エリアを確認しておくことが重要です。
■ポイント④: 保険料と保障内容のバランス評価
月々の保険料負担と保障内容のバランスを考慮することが重要です。掛け捨て型は保険料が安い傾向がありますが、積立型は解約返戻金があるメリットがあります。年齢や経済状況、将来の見通しに合わせて最適な商品を選びましょう。
5. 葬儀社が教える|葬儀保険だけでは不十分な理由と対策
葬儀保険は重要な備えの一つですが、葬儀に関するすべての課題を解決するわけではありません。葬儀会社として数多くの葬儀を執り行ってきた経験から、保険だけでは対応できない側面とその対策についてご説明します。
■葬儀の希望を伝える方法
葬儀保険は金銭的な備えにはなりますが、どのような葬儀を希望するかという意思は伝えられません。希望の葬儀スタイルや宗教、会場などの具体的な要望は、エンディングノートなどに記しておくか、家族に直接伝えておくことが重要です。
■事前相談・事前契約のメリット
葬儀社との事前相談や事前契約には、葬儀保険にはない大きなメリットがあります。具体的な葬儀内容の希望を記録しておけるだけでなく、葬儀社のスタッフとの関係構築により、いざという時に安心してお任せできる環境が整います。
■葬儀保険と預貯金の併用
葬儀費用の準備は、保険だけに頼らず、預貯金と併用するのが理想的です。
保険ではまかないきれない急な追加費用や、葬儀内容の変更にも柔軟に対応できます。年齢や家族の状況に応じて、保険と貯蓄のバランスを調整しておくことが大切です。
また、近年は参列者数の減少により、飲食費や返礼品費用は抑えられる傾向がありますが、その一方でお布施やお墓といった“保険ではカバーできない費用”は依然として発生します。鎌倉新書の調査でも、葬儀総額の中で基本費用以外の支出が大きな割合を占めていることが示されています。
■家族との終活の話し合い方
葬儀についての希望や考えを家族と共有しておくことは非常に重要です。「もしもの時の話をしておきたい」と切り出し、自分の希望を伝えるとともに、家族の意見も聞くことで、互いの理解を深めることができます。話し合いの場は重たくならないよう、日常の会話の延長として持つのがコツです。
葬儀会社の立場から見ると、最も理想的な準備は「葬儀保険」「事前相談・契約」「家族との話し合い」の3つをバランスよく行うことです。金銭的な備えだけでなく、精神的な備えも含めた総合的な終活が、残される家族にとって本当の意味での「備え」になります。
6. 平安祭典の葬儀保険サポート|特徴とご案内
平安祭典では、万一の際に遺族の負担を減らすため、互助会のプランと併用できる葬儀用保険を取り扱っています。一般的な保険会社の商品とは異なり、「葬儀の現場でそのまま使える安心感」が大きな特長です。
特長① 加入しやすさと一生涯の安心
-
- 告知や医師の診査が不要で、持病や通院中の方でも加入可能。
- 満85歳まで申込みでき、加入時の保険料は一生涯変わりません。
例:65歳女性、100歳払済プランの場合、月々4,194円で100万円の保障。
特長② 葬儀費用に直接充当できる仕組み
-
- 保険金は遺族が一度受け取ってから支払うのではなく、葬儀費用に直接振り込みが可能。
特長③ 互助会との併用で負担を最小化
-
- 互助会の掛金プランと組み合わせることで、葬儀費用総額から掛金分を差し引き、さらに保険金を充当。
- 保険金が葬儀費用を上回った場合は、余剰分を受取人にお渡しできます。
特長④ 掛け捨てではない安心感
-
- 多くの葬儀保険が掛け捨て型であるのに対し、平安祭典が扱う「みどり生命・メモリアルⅢ」は解約返戻金のある終身保険型。
- 「保険料が無駄になるのでは?」という不安を軽減しつつ、長期的な備えとして活用できます。
■葬儀社だからこそできる安心サポート
保険会社の視点では「商品説明」が中心になりがちですが、平安祭典では実際の葬儀の流れに直結したサポートをご提供できます。
- 保険金の受け取りから葬儀費用への充当までをスムーズにサポート
- 保険の利用を前提とした費用シミュレーションのご提案
- 「保険だけで十分か?」「預貯金とどう組み合わせるべきか?」といった終活相談にも対応
このように、葬儀保険を“商品”としてではなく、“葬儀に直結する安心の仕組み”として提供できるのが、平安祭典の大きな強みです。
平安祭典では、実際の葬儀に直結する形で安心してご利用いただける「葬儀保険」をご案内しています。
詳細やプランの比較については、下記の専用ページでご確認ください。
7. まとめ:葬儀保険を賢く活用するために
葬儀保険は、遺族の経済的・精神的な負担を減らす有効な手段です。しかし、万能ではありません。
まずは自分の希望する葬儀のイメージを明確にし、必要な費用を把握することから始めましょう。その上で葬儀保険の検討や葬儀社への相談を行い、家族とも希望を共有しておくことが大切です。終活は早すぎることはなく、今日から始めることが将来の安心につながります。
葬儀保険は単なる「保険」ではなく、大切な人生の最期を尊厳を持って締めくくるための「備え」の一つです。経済的な側面だけでなく、精神的な安心も含めた総合的な準備として捉えることが大切です。葬儀会社としては、お客様一人ひとりの希望に寄り添い、理想のお見送りのために必要なサポートを提供していきたいと考えています。
葬儀に関する準備は、残される家族への最後の贈り物でもあります。本記事が皆様の「備え」の一助となれば幸いです。

 平安祭典の事前相談についてはこちら
平安祭典の事前相談についてはこちら 葬儀保険について詳しく見る
葬儀保険について詳しく見る


